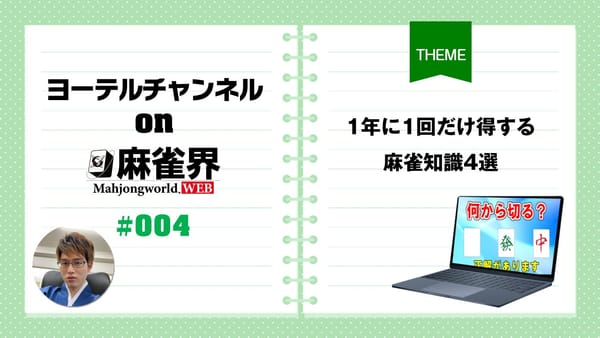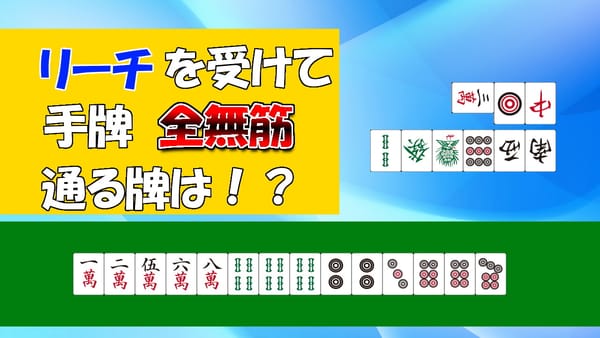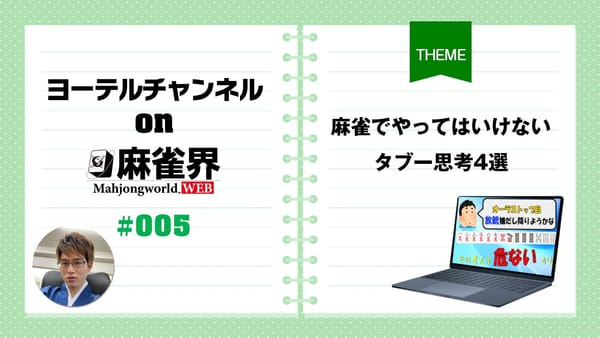
第5回「麻雀でやってはいけないタブー思考4選」
こんばんは、ヨーテルです。 今回は「麻雀でやってはいけないタブー思考4選」というテーマでお話していきたいと思います。 麻雀で勝つために必要な考え方ってなんだと思いますか? これはいろいろあるんですけど、一番大事なのは損得を追求することだと思います。数ある選択肢の中から、一番得なのはどれかなーって考えて選ぶゲームなんですよね。 でも時に、人間はいくつかの合理的でない思考によって、最も得な選択肢を取れなくなる時があります。 そういうのが人間らしさで面白かったりもするんですけど、勝つ上では邪魔なタブー思考ということで4つほど紹介していきたいと思います。 その1:舐め打ち これは大体中級者から上級者になりかけぐらいの人によくあることなんですけど、周りに自分より弱い人が多いみたいな環境に置かれて「こいつになら勝てるやろ」みたいな気持ちで麻雀をする、みたいな。これが舐め打ちです。 この思考に陥るとどうなるかと言うと、負けた時にメンタルを崩しやすくなって、本来の実力を出し切れなくなります。 勝てると思ってる相手に負けるわけですからね、きついといえばキツイです。 でも、これでメンタルを崩